描かれている人物
右上赤丸
煙草屋源七実は坂田蔵人時行
左下赤枠
太田太郎
中央角枠三点
荻野屋八重桐
絵の解説
荻野屋八重桐
左上
恋人からの手紙を貼り合わせた紙衣(かみこ)を着ています。
舞台では紫と黒の地に金糸で文字が縫われた華やかな衣装ですが、
和紙を縫い合わせた着物という設定です。
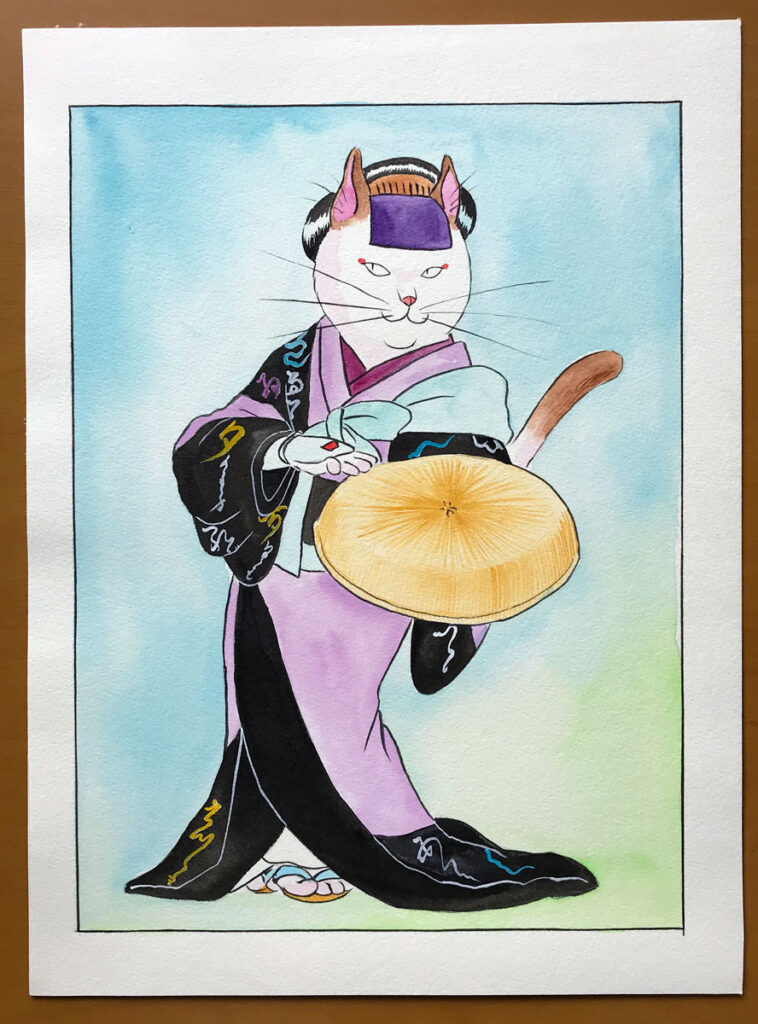
紙衣の八重桐(原画)
中央
時行の魂が体内に入り覚醒した八重桐
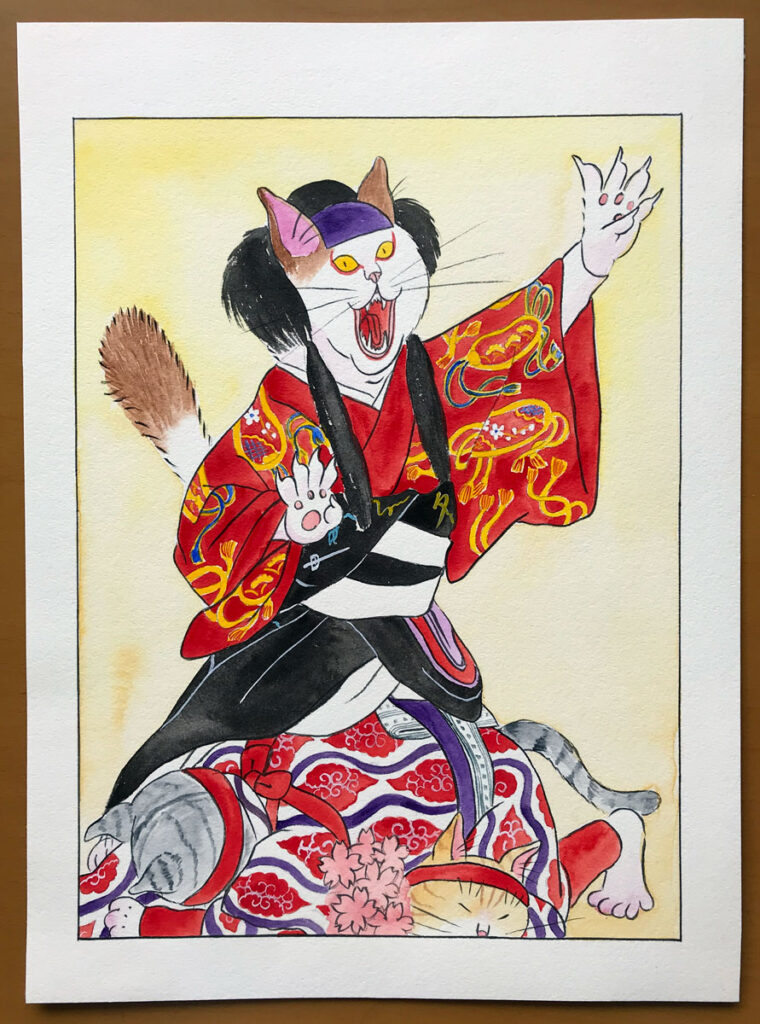
覚醒する八重桐(原画)
右下
沢瀉姫をさらいに来た悪人たちを追い散らす八重桐の立ち回り
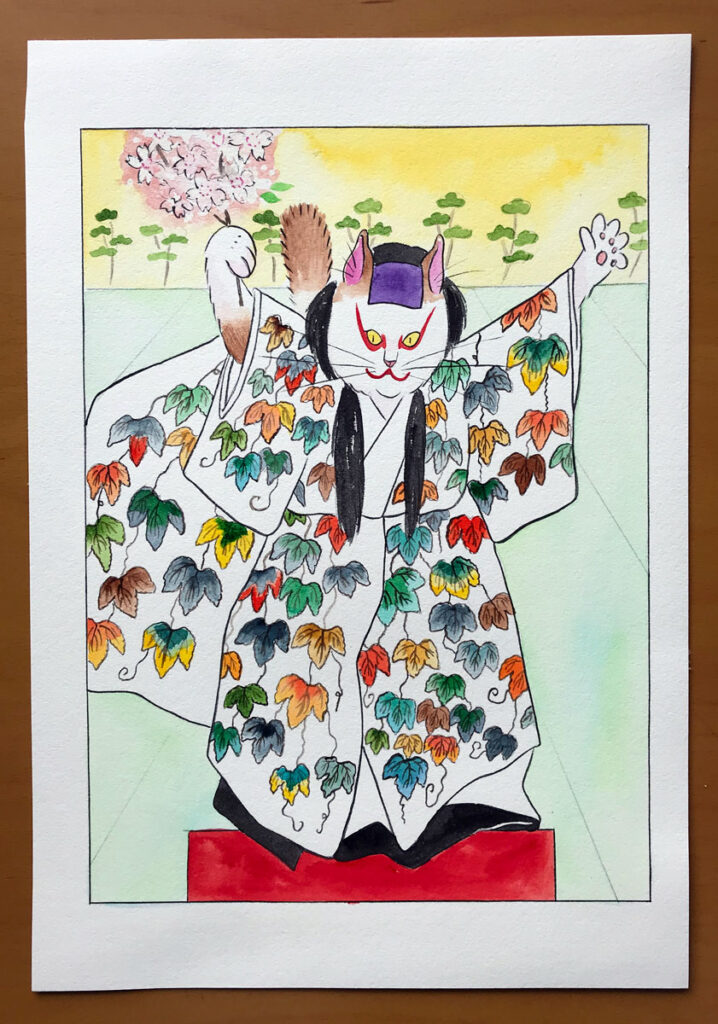
八重桐のぶっかえり(原画)
太田太郎と煙草屋源七実は坂田蔵人時行

左:太田太郎 右:煙草屋源七実は坂田蔵人時行
あらすじ
「嫗山姥(こもちやまんば)」全五段の二段目
近松門左衛門作
通称 八重桐廓噺(やえぎりくるわばなし)
主な登場人物と簡単な説明
・荻野屋八重桐(はぎのややえぎり)
元傾城。坂田時行の恋人。
・煙草屋源七実は坂田蔵人時行(たばこやげんしち・さかたくらんどときゆき)
武士。父の仇討ちの長旅に出、煙草売りとして糊口をしのいでいる。
・太田太郎(おおたたろう)
沢潟姫に横恋慕する右大将高藤の家来。赤っつら。名は三郎や十郎など、その時々で変わります。
・白菊
時行の妹。沢潟姫の家で腰元として働いている。
・沢潟姫(おもだかひめ)
大納言岩倉兼冬の息女。源頼光の恋人。
あらすじ
敵方の陰謀に巻き込まれた源頼光の身を案じる沢瀉姫。
腰元たちは煙草売り源七を館に招き、口上を聴かせて姫を元気つけようとします。
源七は三味線を弾きながら、かつて恋人だった八重桐と作った小唄を披露します。
たまたま館の外を通りかかった八重桐はその小唄を耳にします。
怪訝に思った八重桐は、傾城の恋文の祐筆(ゆうひつ=書記、代筆屋)を名乗り館に入れてもらいます。
八重桐と源七は久々の再会に驚きます。
(*ここで源七が気まずくなって別室に退散する演出もあります)
姫が八重桐の身の上を尋ねると、源七へのあてこすりを長々と語ります。
やがて八重桐と源七は言い争いを始めます。
八重桐は仇討ちは初菊によって既に果たされたと告げると、源七は我が身の軽率さを恥じて切腹します。
今際の際に、死んで八重桐の胎内に宿って生まれ変わると告げます。
そして時行の傷口から焔が飛び出し八重桐の口に入ると、八重桐は気絶しました。
そこに太田十郎が若侍を引き連れて沢瀉姫をさらいにきます。
気絶していた八重桐がムックと起き上がり、姫を攫おうとする侍たちを次々となぎ倒します。
あまりの強さに、太田十郎たちは退散するのでした。
後日譚
超人となった八重桐は足柄山で金太郎を出産します。
私のツボ
”仕形咄(しかたばなし)”通称”しゃべり”
「おたずねのうても言いとうて言いとうて」から始まり、
喋りたおした後に
「あんまり喋って息が切れた。はばかりながらお茶をひとつくださんせ。」
このセリフの箇所、いつも笑ってしまいます。
デザイン会社を作る前、オーダーメイドの仕立の修行をしていたことがあり、そこで知り合った大阪のマダムたちがとにかくしゃべるしゃべる。
「ちょっと言わして」から始まって、八重桐と全く同じセリフを言ってお茶を飲むので、笑った覚えがあります。
淀みなく流れるような話法、あれはもう才能です。
やはり”しゃべり”は上方の伝統芸なのかもしれません。
時行
時行のような役柄はよく歌舞伎に出てきます。
家柄が良さそうで柔和な二枚目。
女性が放っておかないが甲斐性がない。
時行も傾城と深い仲になったほどの遊び人。
煙草売りの口上も、昔とった杵柄です。
しかし家柄など背負うものがあるため、
つっころばしやピントコナとして生きてはいけない。
武士という世間体と、遊び人という本性の間でふらふら定まらない男。
これも和事の立役の一つなのかもしれませんが、近松の人間観察眼には恐れ入ります。
近松のファンタジー
時行の魂が口から入って金太郎を身籠る、という物語が奇想天外で面食らいました。
近松というと心中物がまず思い出されますが、ファンタジー色の強い作品もとても質が高いです。
「傾城反魂香」もそうですし、「雪女五枚羽子板」も幻想的な作品と言えるでしょう。
1700年頃に近松が書いた「浦島年代記」は八重桐と同じように魂が宿って怪童が生まれるという物語です。
「嫗山姥」の初演が1712年なので、「浦島年代記」のアイデアを活かしたのかもしれません。
ちなみに「浦島年代記」は名前の通り浦島太郎伝説をもとに書かれたもので、その怪童の生誕秘話と並行して浦島太郎に似た話が展開します。
「酒の香聞けば前後を忘るる」という酒好きの亀が出てきたり、とても面白いのでお勧めです。
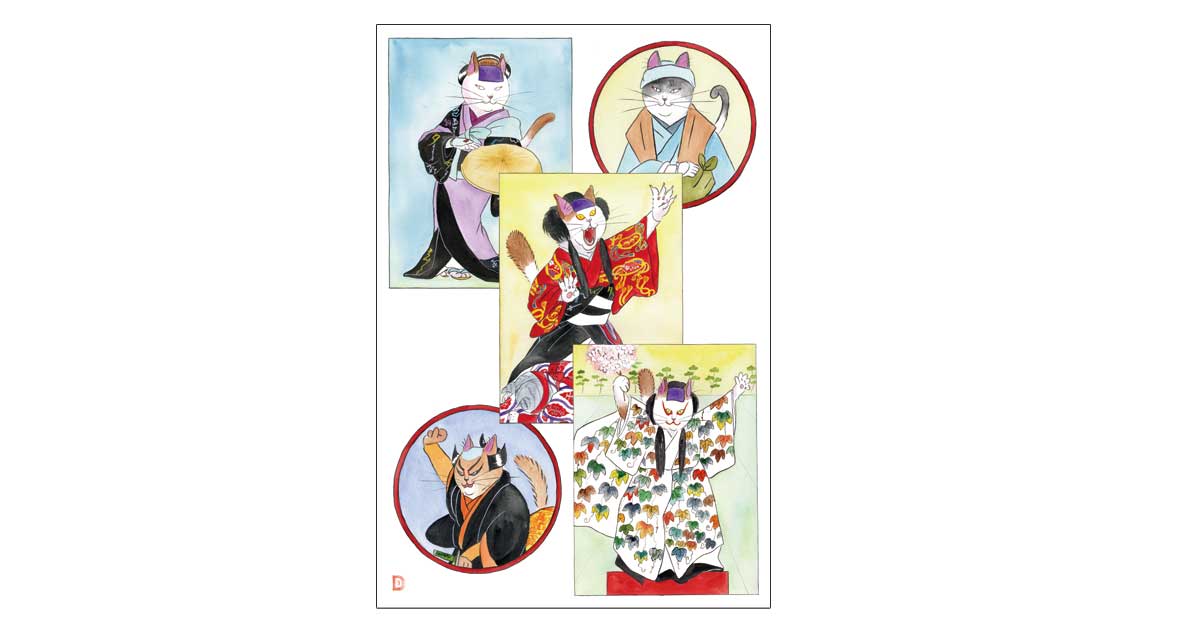


コメント